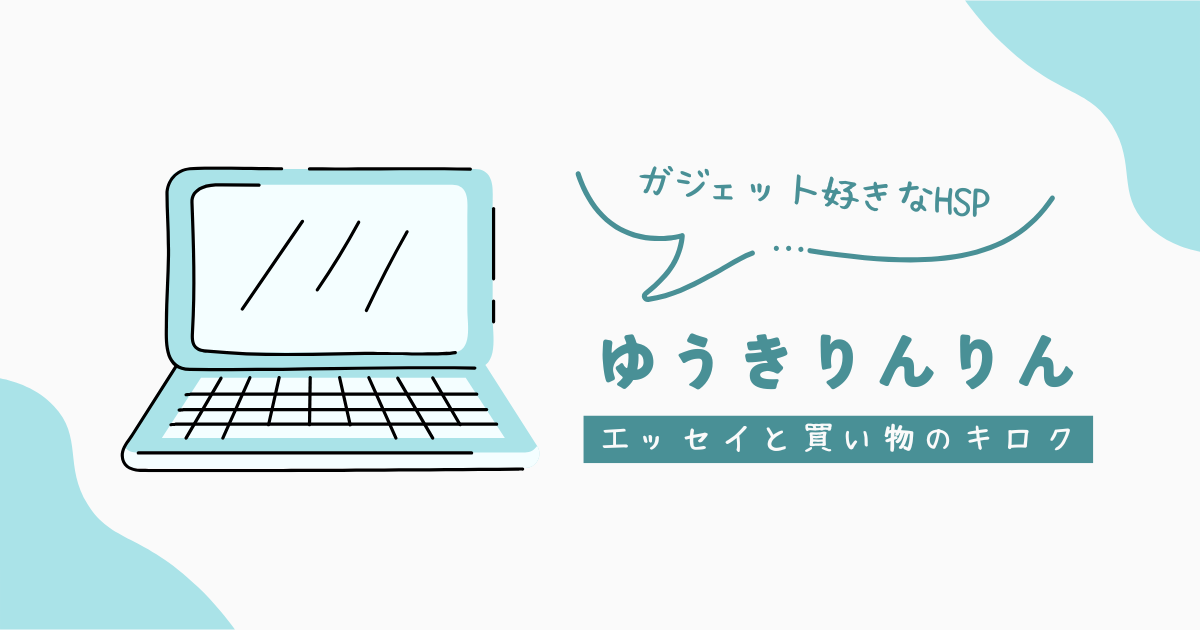新卒で仕事をして初めて「発達障害かもしれない」と感じた
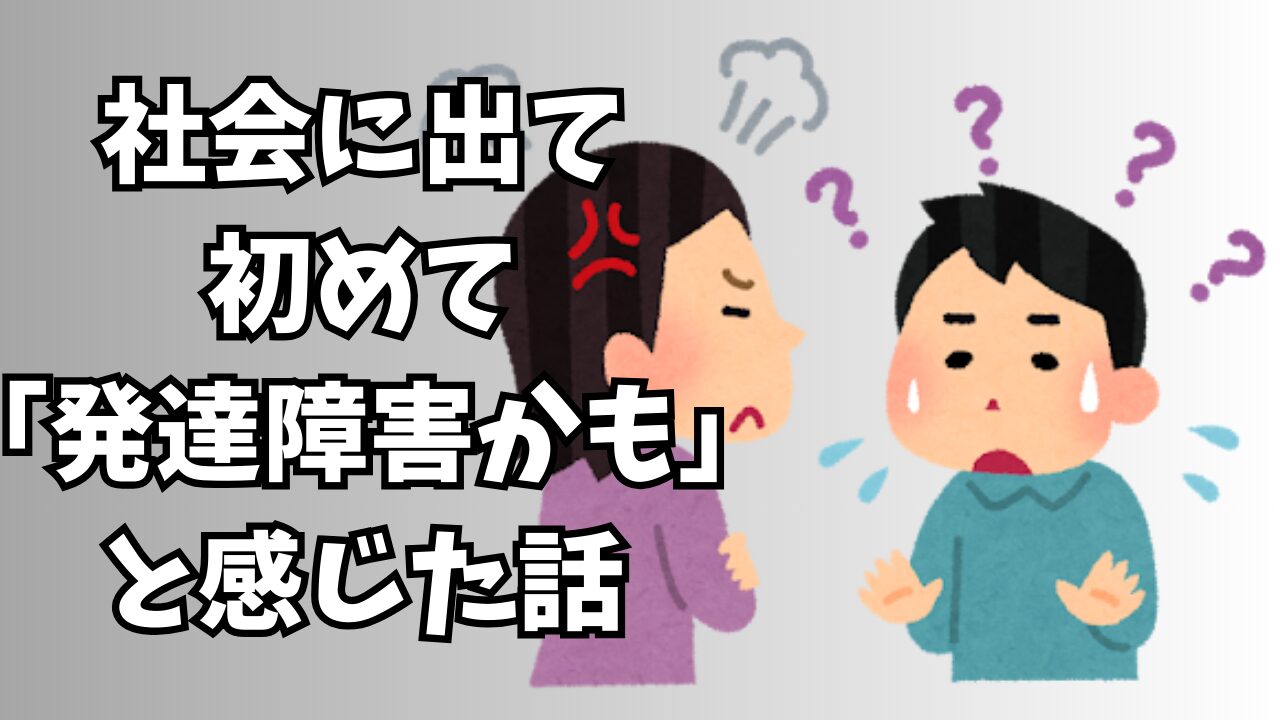
HSP気質なあなたに、この記事はこんな点がおすすめです
4月から働き始めるあなたへ
新しい職場や環境でチャレンジする人へ
「学生のときはできていたのに、社会に出たら全然できなくなった」
という悩みにぶつかったときの、筆者の経験をまとめました
ありがとうございます。りん(@HSP_Rin)です。
90年代生まれのHSS型HSPで、書くことで生きる道を作っていくべく執筆しています。
学生の頃は感じなかったことなのですが、かつて宿坊従業員として新卒で寺院に入寺し、働かせていただくようになった頃から、
「他の人は何てことなくできるのに、自分には全然できない」
「何度指摘されても、教わって納得しても、同じ失敗をしてしまう」
「一つの物事に集中してしまうと、他のことが視野に入らない」
といった気質を強く感じるようになりました。
また、体調を崩してお寺を退職し、社会復帰や生活費のためにと飲食業でのアルバイトを始めたときには、より一層この性質が立ち塞がりました。
●(人と話すことは好きで得意だと思っていたのに)メニューの簡単な説明もできず、忙しいわけでもないのにパニックになり、どもってしまう
●急ぐ必要がない状況で備品を取り出そうとするだけなのに心が勝手に慌てて、ひっくり返してしまう
●頼まれた探し物をしていると、自分の手元しか見えなくなる
探し物は文字通り真横にあるのに、店長から「ここにあるよ」と指さされながら言われているのに、そのことさえ認識できない
こうした経験の積み重ねがあまりにも苦しく、体調との折り合いがつかなかったことも大きいのですが、長く続けられないまま辞めることになってしまいました。
「学生時代は人並みに暮らしていたのに、どうして急にこうなった?」
「短時間のアルバイトもできない自分はどうやって生きていけばいい?」
という問いに悩み続け、現状出した答えがここ、ブログで記事を書くという生き方です。
正直、まだまだ駆け出しで形にできているわけではありません。
ですが、仕事を始めてから前述のような性質にぶち当たり、心身を壊して日常生活もままならくなった私が紆余曲折の末にたどり着いた、大きな答えの一つでもあります。
この4月から働き始めるあなたへ。
この春から、新しい職場や環境でチャレンジする人へ。
「学生のときはできていたのに、社会に出たら全然できなくなった」
「前の職場では簡単だったことが、新しい環境では手につかなくなった」
そんな悩みにぶつかったあなたの一助になりますように、筆者の経験をまとめます。
仕事をするようになって感じた「もどかしさ」
新卒で入った職場(お寺)で陥った感覚
先述した「今までできていたこと」に対する壁や違和感は大学卒業後、新卒で仕事を始めてからはっきり感じるようになりました。
コロナ流行前で外国人観光客も非常に多く、そうでなくても臨機応変がとにかく求められた前職の接客業は、楽しさややりがいももちろんあったのですが、「これまで何てことなかったことが急にできなくなった」と端々で感じ始めたタイミングでもあります。
●先輩方が幾度丁寧に教えてくれても同じ失敗を繰り返す
(その場で真面目に話を聴いてメモを取り、業務の合間や休日に見直してイメージトレーニングを繰り返してもダメ)
●それを乗り越えて「もう覚えた」と思った内容でも、状況がちょっと変わった途端に頭が真っ白になって吹き飛んでしまう
(少し慌ただしくなった途端、「忙しい」という事実で脳内が塗りつぶされ、それ以外の自分の中にある能力の引き出しを開けることができなくなる)
●それまでと少しだけ違う内容を要求されると、内容の変化がわずかな差であってもパニックを起こし、それまでできていた対応すらできなくなる
(これまで「こういうときはAパターンの対応をして」と言われていたことが「今後はA’パターンで頼むわ」と言われるだけでパニック。今までAパターンが難なくできていたとしても、A’の存在を示唆されるだけでAパターンすら遂行不能に)
もちろん、初めての社会人生活だったということや、精神的な成熟や経験も足りない中での毎日だったことは含めるべきかも知れませんが、「自分はこんなに不器用でダメな人間だったか?」と日ごとに自信を失っていった時期でした。
とはいえ、このときは根気強く私に向き合ってくださった職場の方々、まだまだ拙い私の接客を名指しで褒めてくださったお客様の存在など、環境にはとても恵まれていました。
「これまで全然上手くいかなかったけど、過去の自分をアップデートして新しい自分を作れるようになってきた」
「迷惑もかけてきたけど、少しずつできるようになってきた今の自分なら、ここでまだまだやっていけるかもしれない」
そんな風に、仕事への姿勢や苦手の克服が自分の中で形になりつつあったのです。
この職場はその後、身体を壊してしまい休職・退職したのですが、よりによって心身が壊れたのは、失っていった自信が少しずつ再構築できつつあったこのタイミングだったのです。
先輩方やお客様からいただいたものをこれからお返ししていきたいと思っていた矢先の、日常生活もできなくなるほどの体調悪化。
職場へのお返しもできないまま、お客様への還元もできないままの、大きな失意と悔しさを伴った退職でした。
社会復帰を見据えて始めたアルバイトで再度挫折
その後様々な病院を渡り歩き、あらゆる民間療法も試しながら数年にわたって療養させてもらっていました。
しかし改善の兆しが一向に見えず、目減りするばかりの貯金や援助し続けてもらっていることへの焦燥感から、個人営業のレストランで少しの間働かせていただくことに。
そこでは、前項の性質がさらに悪化しました。
混雑もしていない、焦らなくていい場面ですぐパニックになり、簡単なメニューの説明で何度もどもってさらにパニックを加速させ、文字通り目の前にあるものも認識できずに延々と探し続けてしまう自分。
こんな自分をひどく嫌悪し、職場に申し訳なくなるまでそう時間はかかりませんでした。
自分が耐えられなくなったこと、心身の波の不安定さ、その不安定な体調がシフトに影響を与えてしまうことへの申し訳なさからこの仕事も長く続けられず、まもなく退職しました。
前職でも「自分はこんなに不器用でダメな人間だったか?」と日ごとに自信を失っていった時期を過ごしていましたが、このアルバイトでは当時の比ではないほど自分の頭の回らなさを突きつけられ、自信を失うどころか自分という人間を肯定することもできなくなってしまったのです。
日常での自分とAPEXでの自分を照らし合わせてみる
私は先述したお寺を退職してから、APEX LEGENDSというというシューティングゲームを始めたのですが、そこでもこの性質と向き合うことになりました。

詳細は上記リンク先の記事に詳しいのですが、とにかくこの性質が私やチームメイトの足を引っ張り、「ゲームでもダメならいよいよどうしようもない」と茫然自失な状態でした。
しかし、このゲームを通じて旧友や新たな知り合いと毎日顔を合わせるようになり、上達を目指して自分の弱さや長所と向き合い続け、改善や試行を繰り返すことになります。
自分の不出来に絶望し、味方への申し訳なさから何度も投げ出したくなりながら周囲のサポートに支えられ、気がつけば4年半の時が経っていました。
過去の自分ができなかったことをできるようになったときは本当に嬉しかったですし、誰かと協力して物事に取り組むこと、高みを目指すことの尊さや素晴らしさを改めて感じました。
自分の強みが誰かの役に立っていると感じられる経験も、間違いなく不安定な自分を支えてくれた一つです。
「この課題をどう解決するか」といった試行錯誤、「自分は誰かの役に立てる」という喜びなど、健康な人が日々働く中で得ているであろう体験を、私はこのゲームを通じて得ている(得てきた)のだろうと感じます。
提示された「発達障害かも」と「能力の凸凹」
とはいえ、あまりに苦しいこうした性質を完全に受け入れることは難しく、働き始めて変化を感じるようになったタイミングで初めて、「この性質を医療関係者に相談してみよう」と思うようになりました。
「病名のつかない自分の状態を様々な観点から分析してくれるかも」という期待から総合診療科を尋ねるも、「まず最寄りの内科に行ってください」と言われたり。
他方で、言われた通りかかりつけの内科を訪れると「心療内科に行ってください」と言われたり。
お寺を退職したときにも既に経験したのですが、そもそも「心療内科の予約を取る」ことが難しい現代社会で、なおかつ「自分に合う病院や先生を探し続ける」ことには膨大なエネルギーを要します。
当時の私にはそんなエネルギーがなく、それゆえに別の窓口や観点を複数頼ったのですがいずれも突っぱねられてしまい、かなりひどく落ち込んだことを覚えています。
その後、精神科医をしている十年来の友人とプライベートで会ってご飯を食べたとき、藁にもすがる思いで相談に乗ってもらったところ、とても丁寧に向き合って話を聴いてくれました。
病院を頼る気力が完全になくなっていた私は、文字通り本当に救われる思いで、この友人には心の底から感謝しています。
そのとき話してもらったのは、「仕事を始めてから、あるいは管理職に就いてから発達障害を診断される人も多い」という観点。
「40~50代になって役職を担った途端に発達障害の性質を感じるようになり、結果として不安障害を誘発した」という方もいらっしゃるそうです。
これは目から鱗の話で、確かに私はそれまで生きてきた中で、このような方向性で苦しんだ経験はありませんでした。
しかし、働き始めた瞬間からこの壁にぶち当たり、職種や環境を変えてもなお苦しめられ、この厄介な性質はプライベートでも私の前に立ちはだかりました。
「りんは、得意なことと苦手なことの能力的な凸凹が他の人より大きいと思う」という見解ももらい、この点もAPEXで認識した実感と合致しています。
総じて、私の場合は「目まぐるしく状況が変わる状況で視野が狭くなりやすい」のではという仮説にも至りました。
その後、何とか予約できたメンタルクリニックで能力検査の予約を取ることができたため、数ヶ月後に検査を行う予定です。
知能検査や通院を経て、「自分の能力(の凸凹)を可視化する」「それを元に自分を置くべき環境を選定・精査する」「今後の自分が生きていく上での課題やアクションプランを明確にする」ことをしていきたいですね。
この性質をどう活かしてやるか
正直、この性質とは一刻も早く決別したいと思っています。
ですが、それは私自身が別の存在にでもならない限り、難しいでしょう。
なので、いかにこの性質を利用してやるか、ということにシフトすることを目指しています。
例えば日常においても、
「気にしなくてはいけない他の要素が少ない状態」を作り出せれば、「目の前のことに没頭できる可能性が上がる」と言い換えられないか?
これまでの総括として、私はそう思うようになりました。
こうしたブログの執筆や趣味でやっていた動画編集においても、始めるまでは腰が重く別のことを考えていて雑念が多いものの、一度手につけてしまえば気がつくと数時間やってしまえることも多いです。
こういう経験は皆さんもきっとあるかと思いますが、いわば没頭してしまえば「他の要素が視野に入らなくなる」ということ。他の余計なことでパニックになる心配が減ります。
この性質が他人より強く表れるのなら、あらゆる仕事や作業にこれを適用できれば、より集中して取り組めるのではないか、という推測です。
私の場合、「ブログ書くのめんどくさいな……」と一度感じると、
→「あ、そういえばこれやらなきゃいけないんだった」と緊急性の低い小さなタスクを思い出し、そちらへ着手する
→その途中でまた別の小さなタスクに目移りし、何度かこれを繰り返す
→ブログを書くことが後回しになっていく。もしくはしばらくの間完全に忘れてしまう
といったことが頻発します。
なので、それを避けるべく「1文字でいいからブログを書く」という予定を立てた上で、さっさとカフェへ出掛けてしまいます。
「お金を払ってコーヒーを頼んだ」という事実を自らに突きつけ、「周囲には静かに勉強や仕事をしている人がたくさんいる」という状況に自分を放り込んでやるのです。
すると自然と背筋が伸び、一度キーボードに手を伸ばせば、数時間執筆をしていても苦にならないくらい集中できる、ということが増えました。
もちろん、途中で別の調べ物等を思い出して寄り道してしまうことはありますが、それでも自宅で一人で作業するより遥かに効率が上がります。
実際、この記事を買いているのもカフェで、つい十数分前までは体調不良や睡眠不足からダラダラしていました。
しかし、隣の席で熱心に勉強している方を見て我に返り、ひとたびキーボードに手を伸ばしたところ、あれほど重かった腰が簡単に上がり、数十分以上執筆が進んでいます。
- 「無理のない範囲で身銭を切り、多少の痛みを伴って自分の背中を押す」
- 「周囲の環境の力を借りる(間接的なものでも効果はある)」
- 「余計なことを考えなくて済む(考える余地のない)環境に自分を放り出す」
こうしたことを意識しながら、自分という存在を飼い慣らしてやりたいところです。
総じて:自分をどんな環境に置いて生きていくか
些細なことですぐパニックになり、周囲が見えなくなり、適切な言動が取れなくなる。
こんな自分を肯定することはとても難しく、正直、今でも自己肯定感は高くありません。
しかし、自分をどんな状況に置けばパフォーマンスを発揮できるか考えてあげた上でいろいろ試して実践すれば、悩ましい性質とも付き合っていくヒントになるかもしれない。
ゲーム(APEX)での体験だけでなく、お寺・アルバイトでの苦い経験もまた、そう思えるようになるきっかけとして積み上がっていると思います。
書くことが好きで、書くことなら苦難があっても乗り越えられると思うし、乗り越えたい。
そう思った自分を信じて、前後左右に揺れ動きながらも文章を書き続けています。
「(少なくとも今のところは)もうこの道しかない」と強く思っていますし、「この道を選んだのだから、進んでいくしかない」とも決めています。
これは漫画『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の主人公:シン・アスカが覚悟を決めて言い放ったセリフの一つで、私も大きな影響を受けました。
文章を書いて生きていくと決断したときから、彼の言葉を胸に留めて筆を執っています。
読んでくださったあなたにも、あなただけの道が見つかりますように。